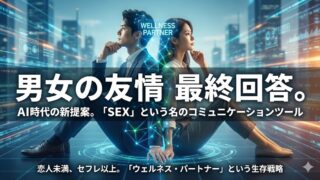 ライフハック
ライフハック 男女の友情は成立する?AI時代の最終回答。「SEX」をコミュニケーションと捉える生存戦略
今日は、古くて新しい、そして永遠のテーマについて、私なりの「少し尖った、でも真剣な」仮説をお話ししたいと思います。
それは、**「男女の友情は成立するか?」**という問いです。
飲み会の席でも、ネット上の掲示板でも、何十年も繰...
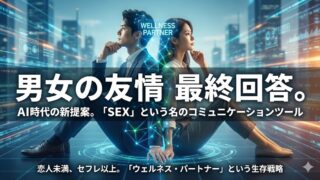 ライフハック
ライフハック  ライフハック
ライフハック  生成AI
生成AI  ライフハック
ライフハック