〜やりたいことがない凡人は奨学金を借りてでも大学に行こう!〜
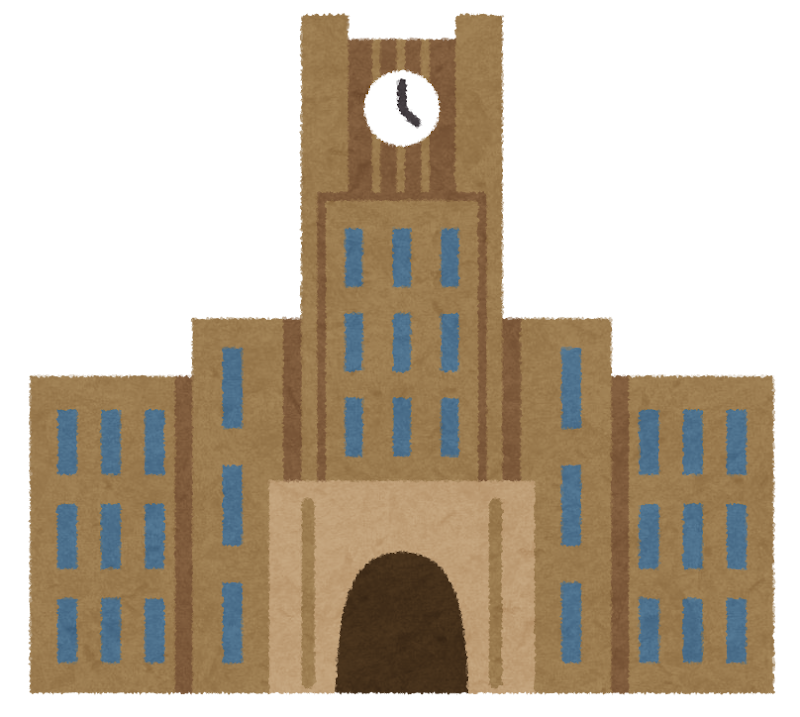
はじめに:私のいちばんの願い
最初に正直に書いておきます。
この文章の前半では、
「大学卒であることで、こんなにハッキリ有利になる」
という具体的な話をいくつか紹介します。
ただ、本当に書きたいことの中心は、
- 奨学金をどう捉えるか
- 若い時間をどう使うか
という部分です。
私は今、
「やりたいことが決まっていない凡人こそ、奨学金を“人生の事業資金”と考えて大学に行ってみてもいいのではないか」
というスタンスを持っています。
高校まで部活や勉強で全力疾走してきた人ほど、息切れしたまま
「何も考えずにそのまま社会人になる」
のは、かなりもったいないと感じています。
人生の選択肢を自分で狭めてしまう危険もあると思うからです。
「いろんな生き方があること」を知ってほしい——。
そんな願いを込めて書くので、ぜひ最後まで読んでもらえたらうれしいです。
目次
- 大卒というだけで受験資格が開く:社会保険労務士の例
- 海外コールセンターで働くときの「ビザの壁」を超えやすい
- 外国籍で日本で働く場合:通訳ビザの条件にも関わる
・一般的なルール
・通訳・翻訳・語学教師は“別枠”扱い - イギリスとシンガポールの「大卒専用ビザ」という現実
・イギリス:High Potential Individual(HPI)ビザ
・シンガポール:Employment Pass(EP)とCOMPASSの「トップ校ボーナス」
・ざっくり比較表 - 大卒(非福祉系)でも、福祉系ダブル資格ルートが開ける
- 奨学金は「人生の事業資金」として考える
・「若い時間」を、“学生”という形で確保するという発想
・JASSOの奨学金は、条件を知ったうえで使う価値がある
・最悪どうにもならなかった場合は、ちゃんと法律が用意されている
① 大卒というだけで受験資格が開く:社会保険労務士の例
「大卒」という肩書きがいちばんわかりやすく効いてくるのが、国家資格の受験資格です。
たとえば社会保険労務士(社労士)。
社労士試験の受験資格はざっくりいうと、
- 大学・短大・専門学校(一定の要件を満たす)などを卒業している
または - 社会保険や人事労務の実務経験が一定年以上ある
のどちらかです。
つまり、大卒であれば「実務経験ゼロ」から、いきなり国家試験に挑戦できます。
逆に、高卒で実務経験枠から受けるなら、
「まず数年どこかで働いてからでないと、受験スタートラインに立てない」
ということになります。
社労士に限らず、ほかの国家資格でも
- 「大卒ならすぐOK」
- 「大卒でない場合は◯年以上の実務経験が必要」
というパターンはたくさんあります。
② 海外コールセンターで働くときの「ビザの壁」を超えやすい
次は、海外のコールセンターで働くケースです。
特に日本語話者向けの求人は、東南アジアだと
- タイ
- マレーシア
あたりでよく見かけます。
実際の求人を見ると、
「日本人向けカスタマーサポート(バンコク勤務)」
応募条件:学士号(Bachelor’s degree)以上(専攻は不問)
福利厚生:ビザ・ワークパーミット支給
とか、
「日本語スピーカー向けカスタマーサポート(クアラルンプール勤務)」
応募条件:日本語ネイティブ+英語日常会話、大学卒歓迎/ビザサポートあり
のような条件がよくあります。
つまり、
「“ビザを出す前提”の正社員枠は、原則『大卒以上』」
と書いてあることがかなり多い、ということです。
東南アジア各国は、外国人に就労ビザを出すとき、
「きちんとした学歴(多くは大卒以上)があるか」
を一つの目安にする傾向があります。
なので、
- 20代のうちに海外で働いてみたい
- 日本語×ちょっと英語くらいで海外を経験したい
という場合、大卒というだけで「選べる求人の幅」がぐっと広がるイメージです。
③ 外国籍で日本で働く場合:通訳ビザの条件にも関わる
今度は逆に、外国籍の人が日本で働く場合の話です。
日本で、いわゆる「ホワイトカラー」として働くとき、多くの人が使うのが
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)
というビザです。
この在留資格は、
- 理工系エンジニア
- 経理・人事・マーケティング
- 通訳・翻訳・語学教師 など
「専門的な知識・スキルを使う仕事」用のビザです。
一般的なルール
基本の条件はざっくり言うと、
- 関連分野を専攻した大学卒・短大卒・専門学校卒
または - 関連業務の長期実務経験(多くは10年以上、国際業務は3年以上)
という形になっています。
つまり、普通は
「勉強した内容(専攻)と、これからやる仕事がそれなりに結びついていること」
が求められます。
もっと具体的に言うと、入管庁のガイドラインでは、
- 「これから従事する仕事の内容」
- 「大学や専門学校で専攻していた内容」
の関連性がチェックされます。
たとえば、
- 企業のマーケティング部門や商品企画で働きたい場合
→ 商学・経営学・経済学などのビジネス系専攻だと説明しやすい - システムエンジニア・プログラマとして働きたい場合
→ 情報工学・コンピュータサイエンス・数学などの専攻が望ましい
といったイメージです(もちろん、実務経験の積み方次第で例外もあります)。
通訳・翻訳・語学教師は“別枠”扱い
一方で、通訳・翻訳・語学教師の仕事については、少し特別扱いになっています。
入管の基準では、国際業務分野について原則、
「従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験」
が必要だとしつつ、
大学を卒業した者が「翻訳・通訳・語学の指導」に従事する場合は、この3年実務要件を免除する
と明記されています。
ポイントを一言でいうと、
- 大学を卒業していない場合
→ 通訳・翻訳・語学教師でビザを取るには、3年以上の実務経験が必要 - 大学を卒業していれば
→ 通訳・翻訳・語学教師については
・「3年以上の実務経験」が免除される
・通訳や翻訳を専攻していなくてもよい(専攻は別分野でもよい)
ということです。
たとえば、
「母国語+日本語が得意な外国人の方」が、日本で通訳や語学教師として働きたいとき、 “大卒”という事実だけで、ビザのハードルがぐっと下がる場合がある
というイメージです。
私は入管実務の専門家ではありませんが、少なくとも
「大卒であるかどうか」がビザの通りやすさに直結する場面が実際に存在する
ということは、知っておいて損はないと思います。
④ イギリスとシンガポールの「大卒専用ビザ」という現実
さらに一歩進んだ例として、
「学歴そのものがビザの条件」
になる国もあります。
ここでは代表的な二つを取り上げます。
- イギリス
- シンガポール
イギリス:High Potential Individual(HPI)ビザ
イギリスには
High Potential Individual(HPI)ビザ
という、「特定の大学卒業者専用」の在留制度があります。
ざっくりいうと:
- 英政府が毎年指定する
世界大学ランキング(QS・Times・上海ランキングなど)上位校のリストがある - そのリストに載っている大学を、過去5年以内に卒業した人は
イギリスの雇用先が決まっていなくても、最長2〜3年イギリスに滞在し働くことができる
という制度です。
日本からだと、東京大学や京都大学などが対象大学として名前が挙がっています(年度によって変動します)。
シンガポール:Employment Pass(EP)とCOMPASSの「トップ校ボーナス」
シンガポールでは、ホワイトカラー向けの就労ビザとして
Employment Pass(EP)
があります。これに対しては「COMPASS」というポイント制が導入されていて、
- 給与水準
- 職務内容
- 企業の多様性
などに加えて、
学歴の評価(Criterion C2:Qualifications)
もポイント化されています。
このC2では、
指定された「トップティア大学・大学院」の学位を持っていると
自動的に20ポイント加算される仕組み
になっています。
日本の大学で、この「トップティア」に含まれているとされるのは、
- 東京大学
- 京都大学
- 大阪大学
- 東北大学
- 東京工業大学
などがあり、近年は特定のMBAとして早稲田・慶應の一部プログラムも取り上げられています。
EP取得にはトータル40ポイントが必要なので、
大学名だけでその半分の20点をもらえる
のは、かなり大きなアドバンテージです。
ざっくり比較表
- イギリス:High Potential Individual(HPI)ビザ
- 仕組み:英政府指定のトップ大学を過去5年以内に卒業
- 大卒条件:指定大学の学位
- メリット:就職先が決まっていなくても英国で一定期間滞在・就労可 - シンガポール:Employment Pass(EP)+COMPASS C2
- 仕組み:学歴を含むポイント制(合計40点必要)
- 大卒条件:指定「トップティア校」学位で20ポイント加算
- メリット:就労ビザが取りやすくなる/条件を満たしやすい
ここで言いたいのは、
「名前のある大学に行け」
という話ではありません。
ただ、世界的に見ると
「大学名そのものがビザの条件やボーナスになる」
ケースが実在する、という事実は知っておいていいと思います。
⑤ 大卒(非福祉系)でも、福祉系ダブル資格ルートが開ける
次は、日本の福祉系資格の話です。
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
この2つは、どちらも国家資格で、福祉・医療・メンタルヘルスの現場ではかなり重宝されます。
大卒(非福祉系)からのルート
福祉系ではない学部を卒業していても、次のような「一般養成施設」を経由すれば、比較的短い期間で受験資格が得られます。
〔社会福祉士の場合〕
- 厚労省指定の「一般養成施設」(昼間/夜間/通信制など)に入学
- 修業年限はおおむね1年以上(多くは1年半〜2年程度)
- 修了すると、社会福祉士国家試験の受験資格が得られる
〔精神保健福祉士の場合〕
同じく厚労省指定の「精神保健福祉士 一般養成施設」(昼間・通信など)があり、
- 4年制大学卒(分野は問わない)であれば
- 1年以上の養成課程で受験資格を得られるコース
が用意されています。
〔ダブルライセンスへの近道イメージ〕
さらに、一部の専門学校や通信課程では、
- すでに精神保健福祉士を持っている人が
1年程度の追加履修で社会福祉士も取れる - あるいはその逆(社会福祉士 → 精神保健福祉士)
を想定したコースもあります。
ゼロからいきなり「1年で両方とも取得」は現実的ではありませんが、
- まず精神保健福祉士の一般養成(1〜1.5年)
- その後、追加1年で社会福祉士養成(または逆ルート)
という形で、合計2〜3年ほどでダブルライセンスに到達するルートは、
大卒(非福祉系)だからこそ狙えるショートカット
と言えます。
大卒でない場合との違い
一方、大卒資格がない場合は、
- 福祉系の4年制大学に入り直す
- 福祉系短大+実務経験+養成施設
- 長期の実務経験+養成施設
など、どうしても「年数」か「実務経験」が重くのしかかるルートが多くなります。
ここでも、
「とりあえず大卒」を持っておくだけで、後から方向転換したくなったときのルートが一気に増える
というのは、大きなポイントだと感じます。
⑥ 奨学金は「人生の事業資金」として考える
ここからが、私がいちばん伝えたい部分です。
「若い時間」を、“学生”という形で確保するという発想
私は、
「奨学金 = 単なる借金」ではなく、「自分の人生の事業資金」
と考えています。
多くの人は、大学を出て就職すると、
- お金は毎月それなりに入ってくる
けれど - 使える時間・じっくり考える余白は、一気になくなる
という状態になりがちです。
だからこそ、まだ10代〜20代前半で、
- やりたいことがよくわからない
- 部活や勉強で走り続けて、むしろちょっと燃え尽きている
という人ほど、
無理に「すぐ就職」を選ぶのではなく、
「学生」という、社会からも受け入れてもらいやすい立場で若い時間を確保する
という選択肢を、真剣に検討してもいいのではないか、と私は思っています。
高校まで部活などで突っ走って、心も身体も疲れている状態で、
何の考えもなく社会人として働き始めてしまうと、
- 自分は本当は何を大事にしたいのか
- どこでどう生きていきたいのか
を考える余白がないまま、気づけば年だけ取っていた……となるリスクもあります。
奨学金で生活の最低ラインを確保しながら、
- 勉強に振り切るもよし
- とことん遊んでみるもよし
- あえて「何もしない時間」を意識的に作るもよし
だと私は感じています。
JASSOの奨学金は、条件を知ったうえで使う価値がある
日本学生支援機構(JASSO)の第二種奨学金(有利子)は、
- 利率は上限が決められていて、民間ローンより低めに抑えられている
- 利率の方式も「利率固定方式」と「利率見直し方式」から選べる
- 貸与中・在学猶予中・返還期限猶予中は、利息がかからない期間がある
といった特徴があります。
返還が苦しくなった場合には、
- 減額返還制度(毎月の返還額を一時的に半分・3分の1などに減らし、期間を伸ばす)
- 返還期限猶予(一定の条件で、返還そのものを待ってもらう)
といった制度も用意されています。
もちろん、
「安いからどんどん借りろ」
という話ではありません。
ただ、条件をきちんと理解したうえで、
「若い時間を買う」選択肢として使う価値は十分にある
と私は感じています。
最悪どうにもならなかった場合は、ちゃんと法律が用意されている
それでも、人生には予想外のことが起きます。
- 病気になった
- 家族の事情で働けなくなった
- 思った以上に収入が伸びなかった
そんなときの「最後の最後のセーフティネット」として、日本には
- 自己破産
- 個人再生
など、法的な債務整理の制度も用意されています。
自己破産のデメリットとしてよく挙げられるのは、
- 官報に名前が載る
- 一定期間、クレジットカードが作りにくくなる
- 一部の職種に就けない期間がある
といった点です。
たしかに、これらは決して軽くはありません。
でも、思い切ってポジティブに捉え直すと、
- 官報を日常的にチェックしている人は、実際にはそう多くない
- クレジットカードの代わりにデビットカードやプリペイドカードを使う手もある
- 「一定の職種」以外にも仕事はたくさんある
とも言えます。
もちろん、
「じゃあどんどん破産しよう」
という話ではまったくありません。
ただ、
「どれだけ失敗しても、やり直しの制度が一応ちゃんと用意されている社会なんだ」
という感覚を持っているだけでも、
- 進学や留学
- 転職や起業
- 新しいチャレンジ
に対する心理的なハードルを、少し下げてくれると私は思います。
つまずいても、やり直して、また社会に関わり直していけばいい
私は、たとえ奨学金の返済やお金のことで大きくつまずいてしまったとしても、
また1からやり直して、少しずつ社会に貢献していけば、自分の失敗もいつか受け入れられるようになると感じています。
最初のうちはきっと、
「なんでこんな選択をしてしまったんだろう」
「自分はダメな人間なんじゃないか」
と、自分を責める気持ちが大きいかもしれません。
でも、時間が経つ中で、
- 目の前の仕事をちゃんとこなして、誰かに「ありがとう」と言われた瞬間
- 税金や社会保険料をきちんと払い続けている自分に気づいたとき
- 家族や友人、後輩など、身近な誰かの役に立てたと感じる場面
そういう小さな出来事が少しずつ積み重なっていくと、
「失敗した自分」=「終わった自分」
ではなく、
「失敗も含めて今の自分をつくっている一部なんだ」
と、だんだん物語の中に組み込めるようになっていきます。
一度つまずいたからといって、人としての価値が消えるわけではありません。
やり直すチャンスにちゃんと手を伸ばして、もう一度、自分なりの形で社会に参加していくこと。
その積み重ねが、いつか
「過去の失敗も含めて、自分の人生だ」
と思える日につながっていくと、私は信じています。
そして、こうした考えを少しでも持つことができれば、
「人生が詰んだ」「もう終わりだ」
と感じてしまって、自分の命を手放そうとしてしまう人も、わずかでも減るのではないかと、個人的には思います。
おわりに
ここまで、
- 大卒であることで開ける具体的なメリット
- ビザや国家資格という、わりと“固い”話
- 奨学金を「人生の事業資金」として捉える考え方
を書いてきました。
私は、
「誰もが大学に行くべき」
と言いたいわけではありません。
ただ、
「やりたいことが決まっていない凡人」こそ、奨学金を使ってでも一度ゆっくり考える時間を確保してみてもいいのではないか
とは、本気で思っています。
そして、この考えを少しでも共有できる人が増えれば、
人生で苦しんだ時に自殺を選ばずに済む人も、きっと今より増えるのではないか——と、私は願っています。

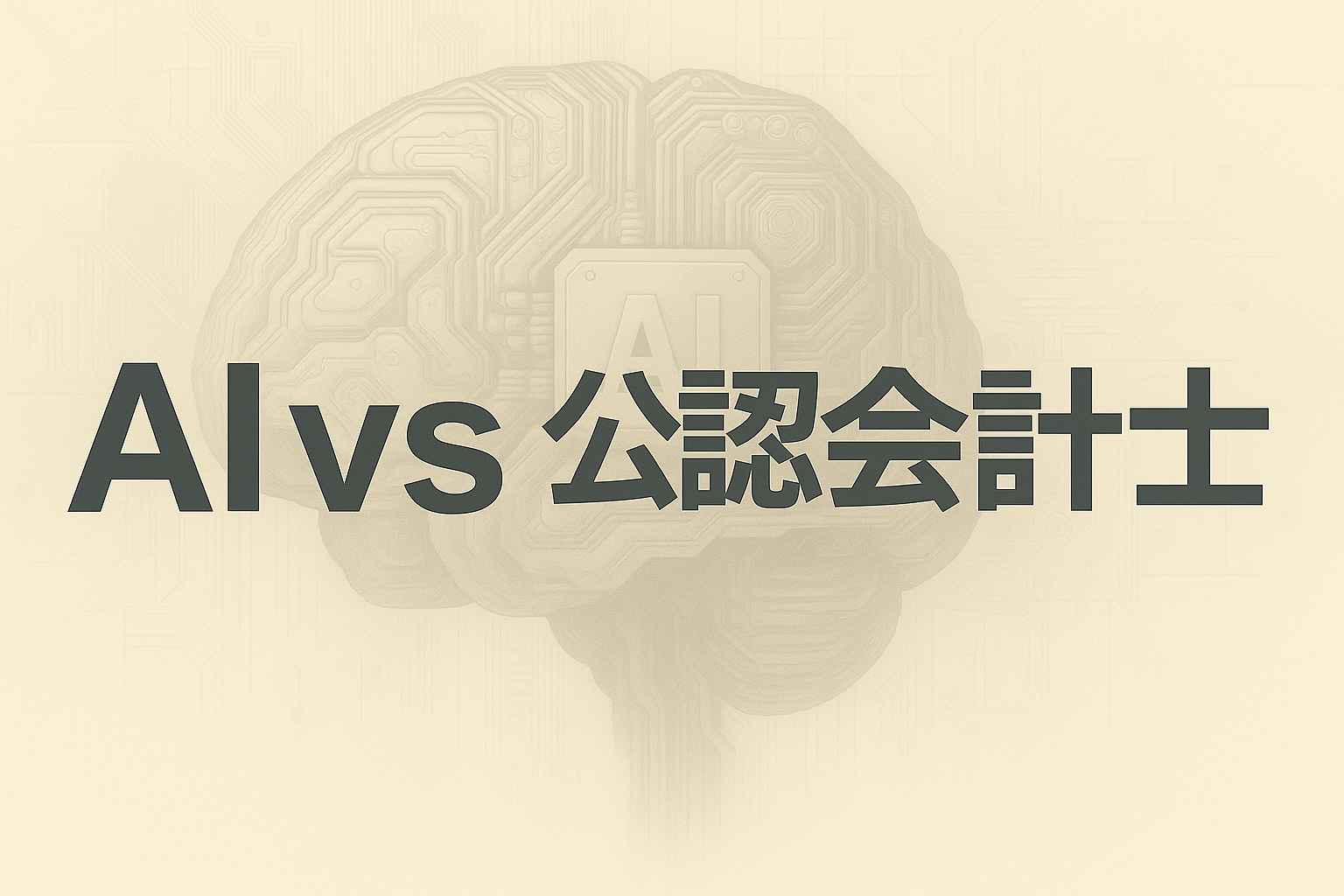
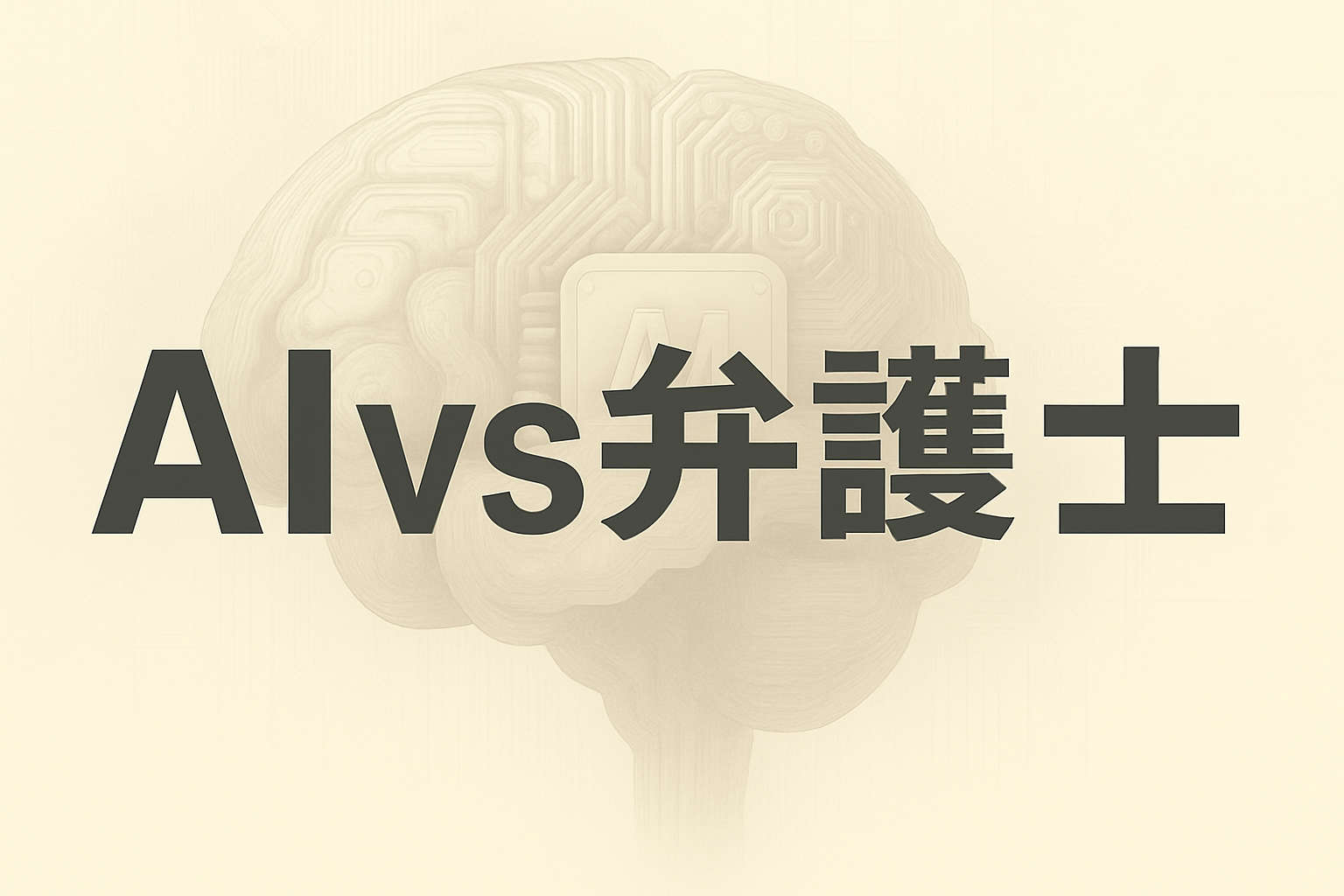
コメント