 ライフハック
ライフハック 【野村克也×NEW KAWAII】見た目の若さに疲れた人へ。「老いない心」を作る究極のマインドセット
「最近、鏡を見るのが憂鬱……」 「アンチエイジングやルッキズム(外見至上主義)という言葉に疲れ果ててしまった」
そんなふうに、年齢を重ねることへの恐怖や、見た目の若さへのプレッシャーを感じていませんか?
実は、「本当の若さ」は...
 ライフハック
ライフハック  「仕事・マインド」
「仕事・マインド」 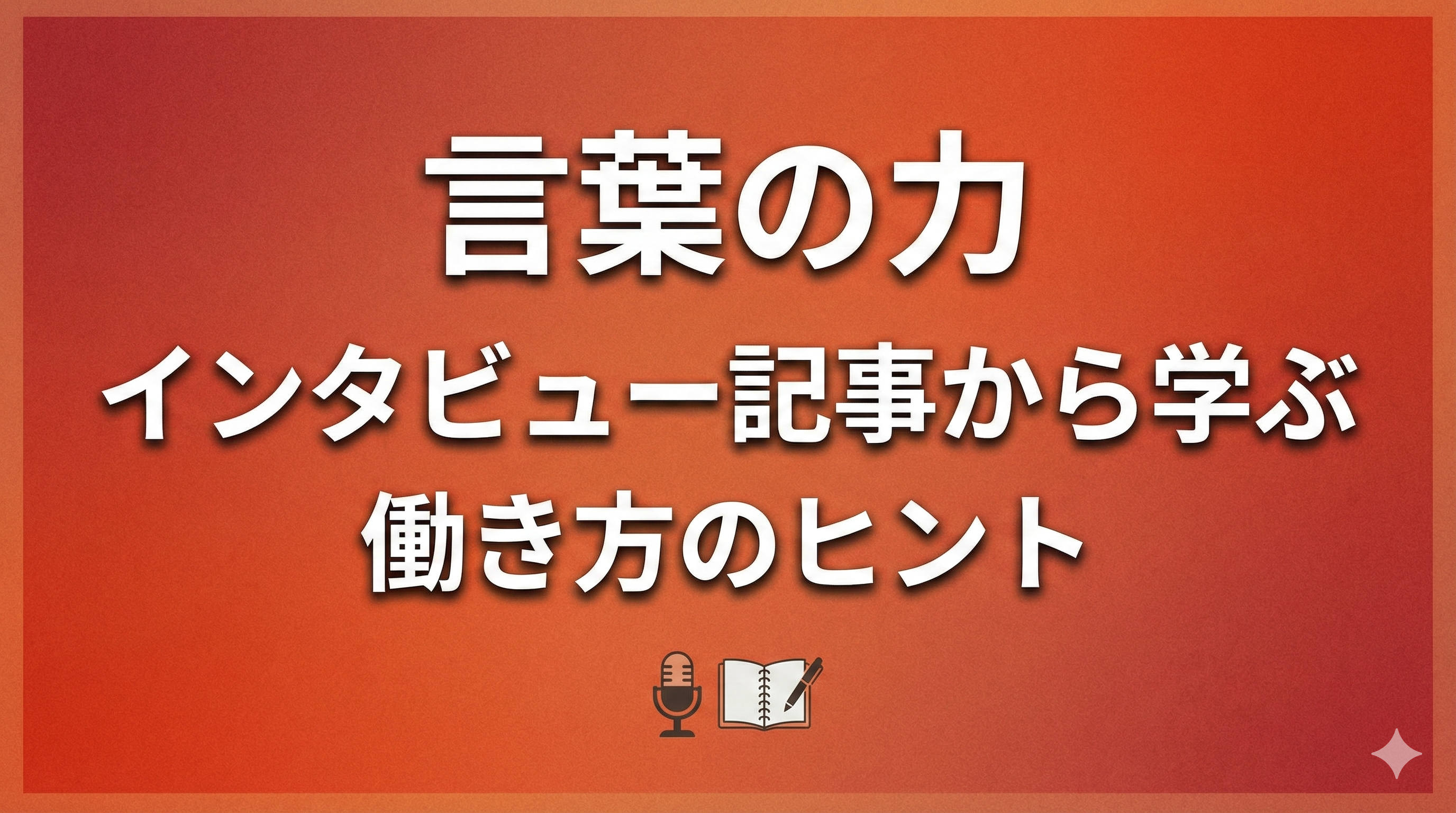 「仕事・マインド」
「仕事・マインド」 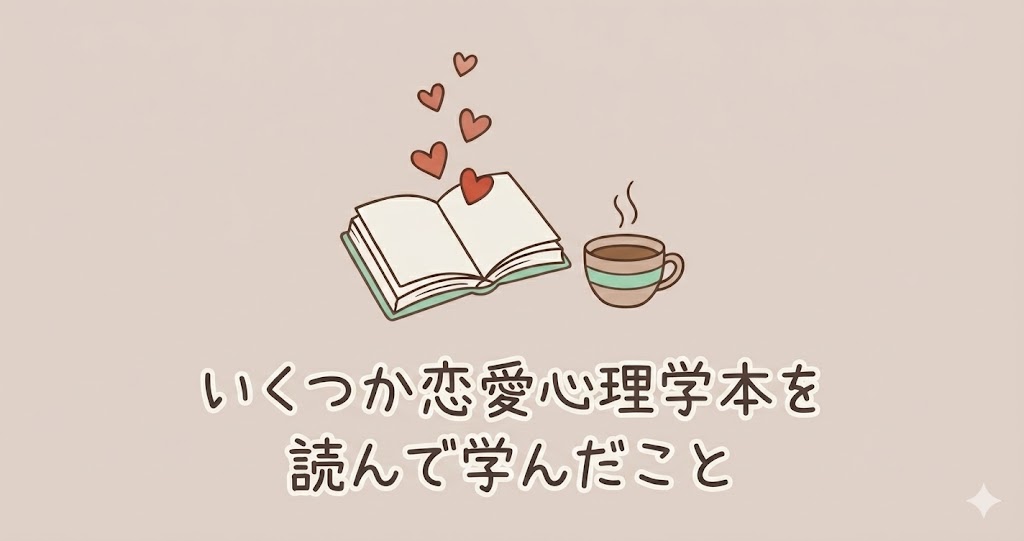 「仕事・マインド」
「仕事・マインド」  「仕事・マインド」
「仕事・マインド」 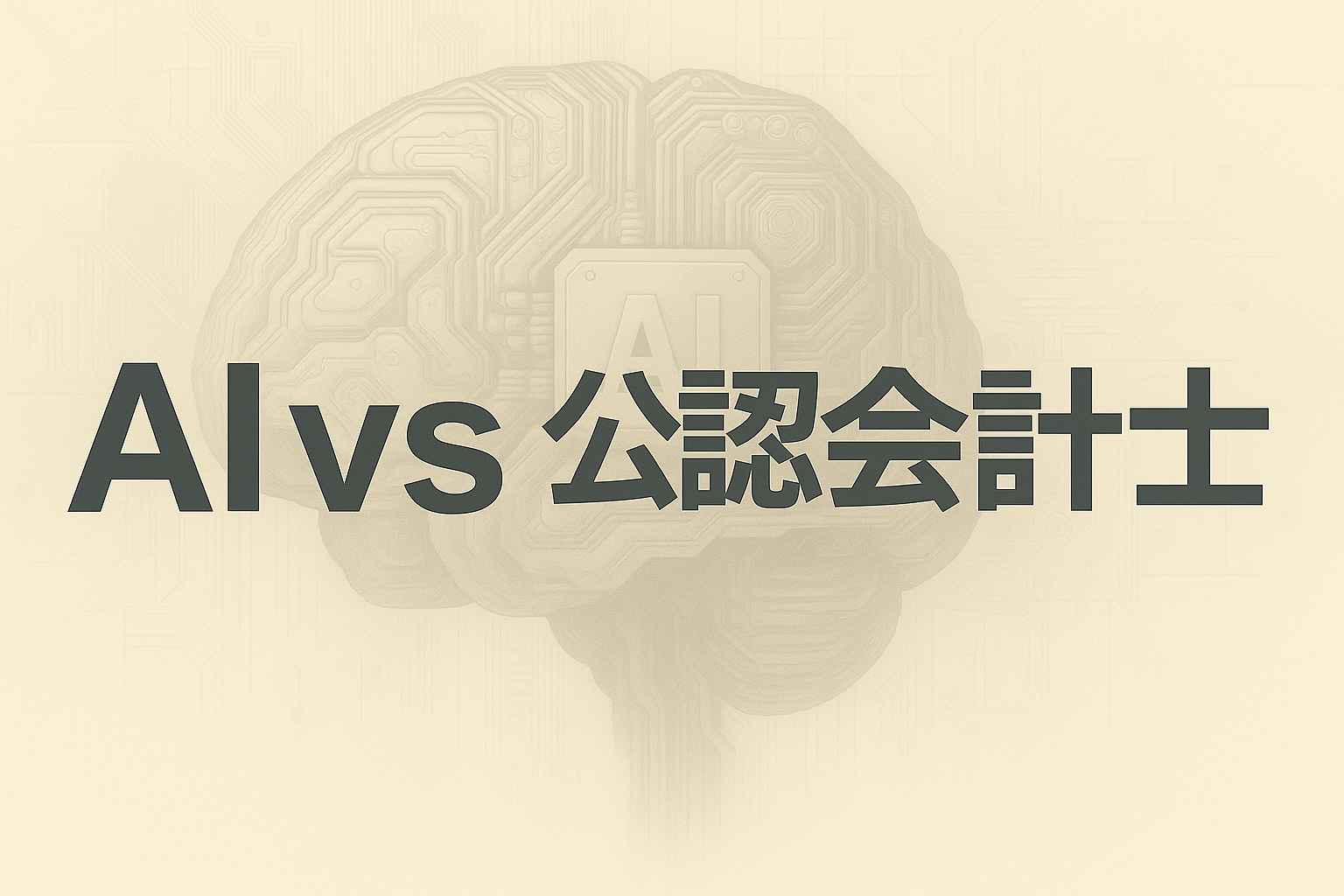 生成AI
生成AI 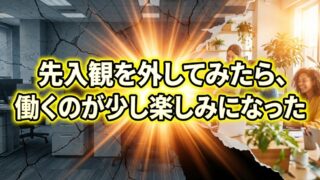 ライフハック
ライフハック