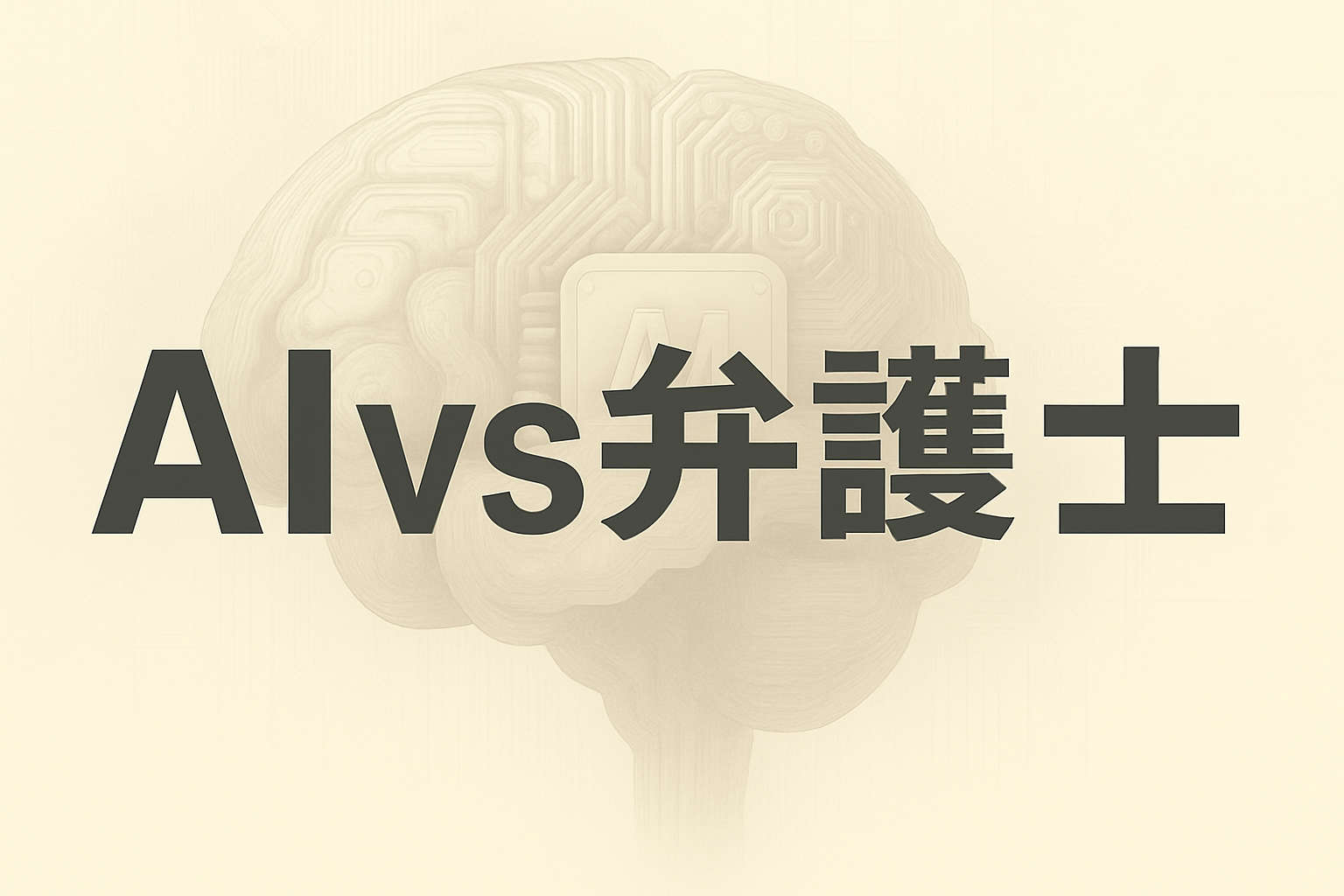 生成AI
生成AI 生成AI時代、弁護士に本当に必要なのは「知識量」より「交渉力」と「メンタルの強さ」かもしれない
はじめに:ここでいう「弁護士」とは?
ChatGPT をはじめとする生成AIが広がってから、
「そのうちAIが判例も条文も全部出してくれるし、弁護士いらなくなるんじゃない?」
という話を聞くことが増えました。
...
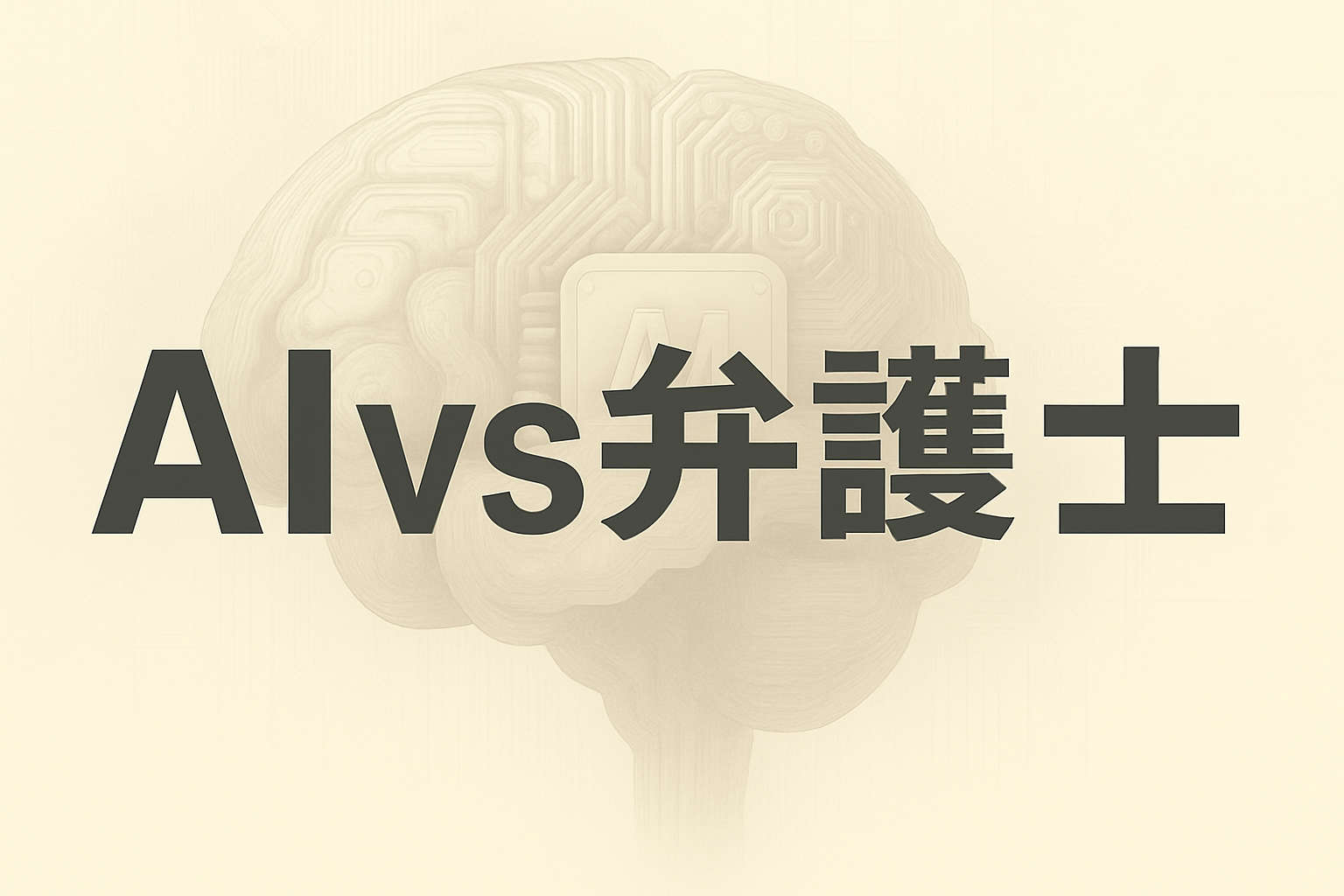 生成AI
生成AI 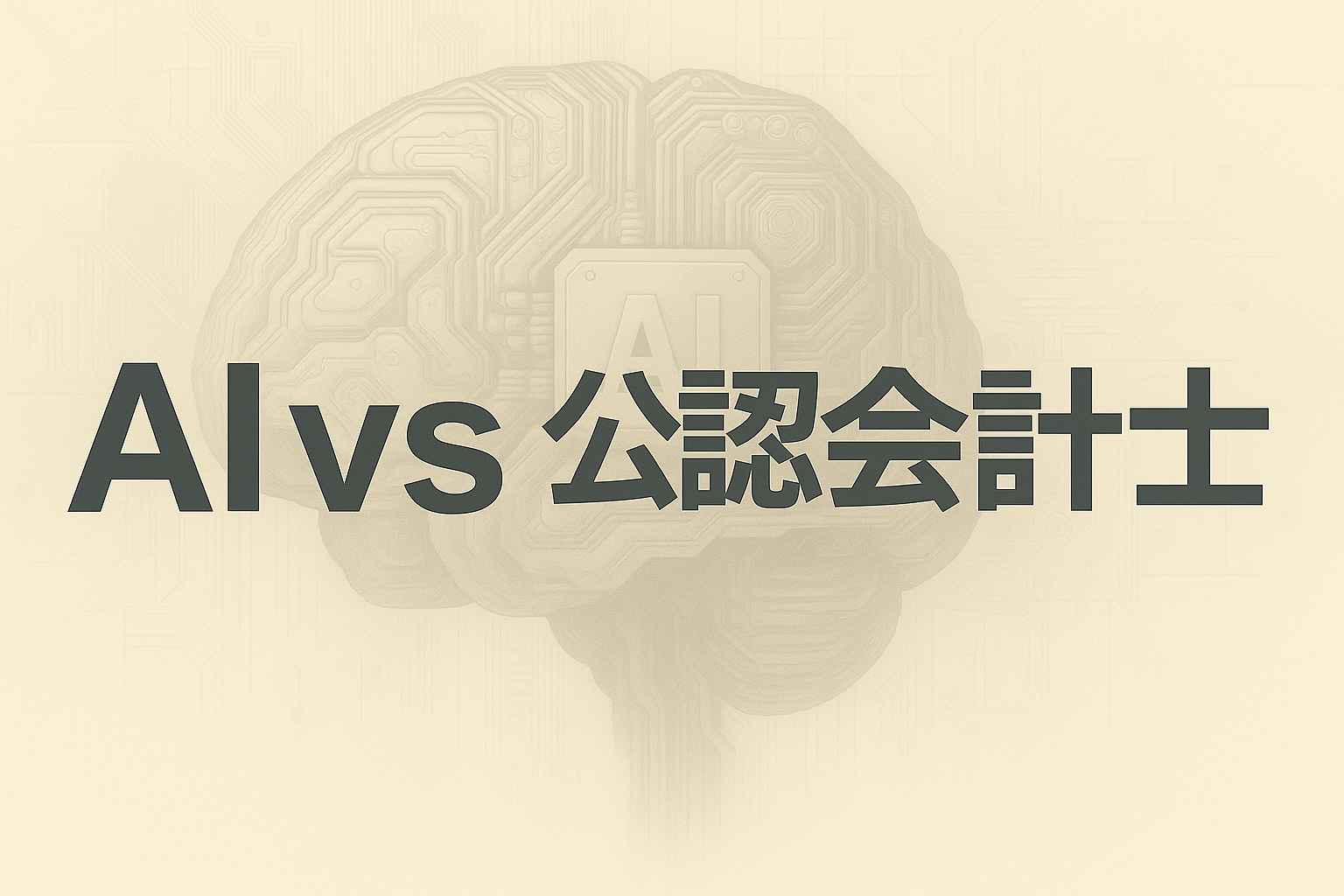 生成AI
生成AI